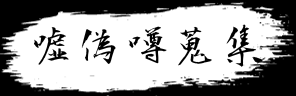【オカルト】海に現れ船を破壊する巨大な入道「海坊主」
今回は海にまつわる妖怪の中でも特に知名度の高いモノ「海坊主」を紹介しよう。
海坊主とは

歌川国芳 – http://visipix.com/cgi-bin/view?s=5&userid=1616934267&q=%272aAuthors/K/Kuniyoshi%201797-1861%2C%20Utagawa%2C%20Japan%27&u=2&k=1&l=en&n=492, パブリック・ドメイン, リンクによる
海坊主(うみぼうず)は、日本の伝承に登場する海に住む妖怪だ。
海法師(うみほうし)や海入道(うみにゅうどう)とも呼ばれ、船を破壊するとされる異形の存在とされる。
通常は夜間に現れ、穏やかだった海面が突然盛り上がり、巨大な黒い坊主頭のような形をした妖怪が出現すると伝えられている。
海坊主の大きさは目撃談によって様々で、数メートルから数十メートル、場合によっては数キロメートルに及ぶとも伝えられている。
また、川に出現したり、上陸したりする話もある。
海坊主に関する伝承は地域によって異なり、魚が化けたもの、海で遭難した者の亡霊、あるいは自然現象を誤認したものなど、その起源については多くの説があるとされる。
海坊主は、船を沈めるために「杓子を貸せ」と言って現れるとされる船幽霊と同一視されることもあるが、海坊主が現れる際には必ずしも海の異常が伴わないという点で区別されることもある。
海坊主を見た後に天候が荒れ始めるなどの怪異が訪れるともされ、異常現象が起こる前触れともみなされる。
伝承によると、海坊主は煙草の煙が弱点であり、遭遇した際にはこれを用いることで助かるといわれている。
また、東北地方では漁で最初に採れた魚を海の神に捧げる風習があり、これを破ると海坊主が船を壊し、船主をさらっていくといわれている。
現代でも、海坊主は日本の文化や創作物の中で人気のある妖怪の一つとして語り継がれており、名前だけで言えばシティーハンターにも登場している。
日本各地の海坊主の伝承
海坊主に関連する伝説は、日本の各地に残る多く残っている。以下いくつかの有名な伝説を紹介しよう。
東北地方の伝承
東北地方では、漁で最初に採れた魚を海の神に捧げる風習がある。この風習を破ると、海坊主が船を壊し、船主をさらっていくと言われている。
青森県下北郡東通村の伝説
ここでは、フカに食われた人間が「モウジャブネ」という存在になるとされ、味噌を水に溶かして海に流すことで海坊主を避けることができると伝えられている。
佐渡島の「タテエボシ」
佐渡島には、海から立ち上る高さ20メートルもの怪物「タテエボシ」が船目掛けて倒れてくるという伝説がある。
鳥取県の「因幡怪談集」
江戸時代に書かれた『因幡怪談集』には、海辺で周囲2尺ほどの棒杭のような形をした一つ眼の怪物と出会う話が残っている。この怪物が海坊主だと考えられている。
宮城県の気仙沼大島
ここでは美女に化けた海坊主が人間と泳ぎを競ったという話がある。岩手県にも同様の伝説がのこっており、誘いに乗って泳ぐとすぐに飲み込まれてしまうとされる。
これらの伝説は、海坊主がどのように日本の各地で恐れられ、語り継がれてきたかを示している。
海坊主は、自然現象や海の生物を誤認したもの、あるいは海での遭難者の亡霊など、さまざまな起源を持つとされているが、実際に海で起こった現象を妖怪になぞらえて残している可能性もあるだろう。
※全て嘘で全て偽、信じるかはアナタ次第だ